一般的な受験生がこの質問にどう答えるか考えてみよう。 おそらく合理的な説得、親の立場理解、患者の親との共感などについて答えるだろう。 ここで前述したことが全て正解に近いはずなのに、なぜこのような問題を出すのか指摘しなければならない。 受験生、まもなく予備医大生になぜこのような問題を要求するのか考えてみよう。 実際、このような状況はベテラン医師でも簡単に解決策を語ることはできないだろう。 正解がない状況だ。 そのため、この状況を一つ一つ分析しながら接近する必要がある。 必ず考慮すべきことはキーワードに対する分析と整理をしなければならない。 ここで「インターン」という単語を考えてみよう。 医術を学問的にのみアプローチするのか。 それとも臨床経験まで考慮して判断してみるのか? 学問だけでアプローチすれば、医学部教材に出てきた知識を学んだばかりのインターンの行動が患者や患者の両親に問題になることはないだろう。 自分の体を任せなければならない患者の立場から考えると、頭の中に覚えた医療知識が全ての医師と医療知識をもちろん、臨床経験が豊富な医師のうち誰に信頼を送るのかという点だ。 この問題は医大志望生に卓越したインターンが繰り広げるソロモンの知恵のような素敵な答えを求めるものではない。 具萬里(ク·マンリ)のような医術の道、その入り口に立っている受験生に謙遜と医学部進学の覚悟と意志をうかがわせる質問と見ることもできる。 *エデュジン記事URL:http://www.edujin.co.kr/news/artileView.html?idxno=40833記事に移動する際、本記事URLを必ずご記載ください。

*出典:「面接のラスボス」|夢の靴教育プラットフォーム「夢の靴」教育プラットフォームは、教育情報から疎外された地域に均等に情報を共有し、公教育の上向き平準化のために努力する企業です。 全国の先生と生徒の未来を助けるために努力しています。 「夢の靴教育プラットフォーム」プログラムおよびコンテンツに関するお問い合わせ 010-2618-0187
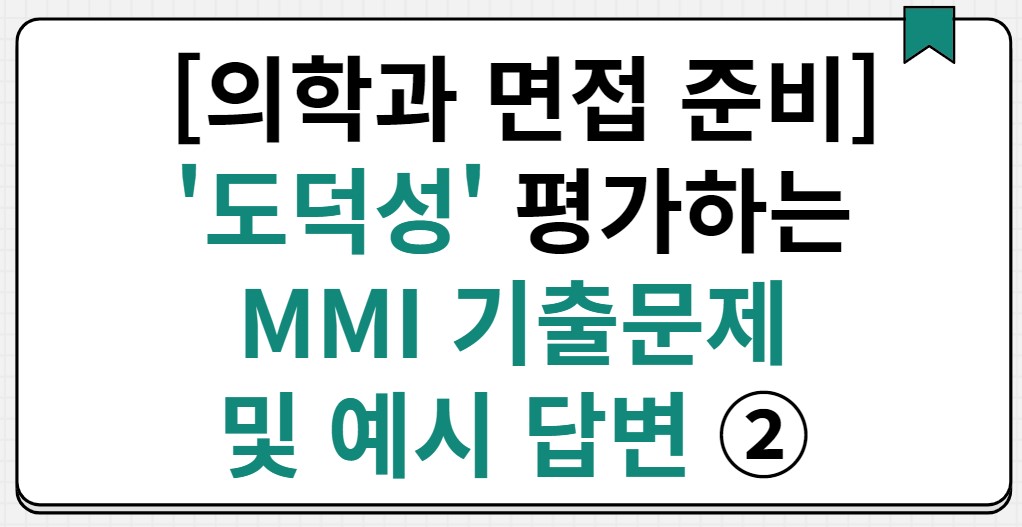
ある夜、両親が交通事故に遭った子供を連れて急いで救急室に来た。 子供の状態はそれほどひどくなく、先に来たより重い患者を見るために診療が遅れているため、両親が救急救命室の医療スタッフに怒っている。 1。 本人が医大を卒業してその救急室に勤務するインターンの場合、怒る親にどのように状況を説明するのか。 2.親たちが怒って心配する理由は何だと思うか?3.親たちはその状況で救急救命室の当直医であるあなたにどうしてほしいと思うか?4.この状況で医師として最も適切な行動は何だと思うか?

医師にとって患者に対する共感と理解能力は非常に重要な力量だ。 情緒的に困難な状況で意思疎通は重要だ。 相手の感情を理解し、考慮して自分の感情と考えを伝えることができるかを評価する。 医予科志願者はまだ社会経験が豊富ではないので、過去にあった状況でどのように行動していたかを確認することは適切ではない。 個別面接の類型の一つである状況面接(Situational interview)を進め、どんなことが起きると仮定した時、どのように行動するかを問うことで共感疎通能力を評価する方式を主に使う。 このような質問は正解がないため、回答ガイドを例示回答の代わりに提供する。 このような質問は他人に対する共感能力、効果的な意思伝達方式を要求する場合だ。 他人の立場で考える能力と疎通方法も同時に把握する。 本人中心より他人の立場で問題を眺めて話し、公共の価値、違法なことなのかどうかに基づいて答えなければならない。 面接質問1

* 夢靴教育 2学期進路転換期キャンプ申請 [バナークリック]
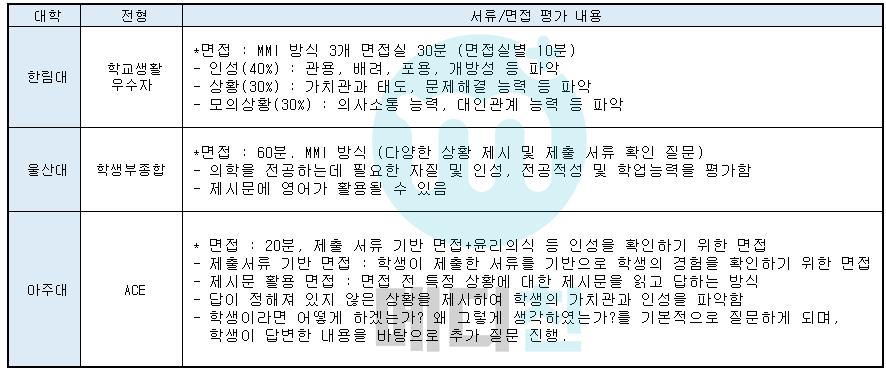
「共感疎通」問題を単純に同情したり相手の状況を理解する程度と考えてはならない。 共感と疎通の核心には合理性が前提にならなければならないためだ。 このような質問に答えるためには、提示されたキーワードの抽象的な状況や概念をどれだけ具体化して合理的な答えができるかがカギだ。 したがって、このような質問を受ける場合、キーワードと関連してまずいくつかを考えてみた後、答えを考えてみることが望ましい。 第一に、「基礎生活受給者」という概念と抽象的に考えている「貧困」にはどのような違いがあるのか? 第二に、国や社会は救済対象を決定するためにどのような客観的基準を設けるべきか。 第三に、客観的基準に合致しない「経済的危機状況」をどのような基準で補完できるのか。 以上3つ程度で分析した後に答えればはるかに良い答えが出るだろう。 悔しさが前提になったり、状況の中の感情に移入しては、良い返事が出るのが難しいことを肝に銘じなければならない。 面接質問2A、B、Cは親しい大学の同期たちだ。 Cは家庭の事情が厳しく基礎生活受給者であり、このような学生たちを対象にする奨学制度があって奨学金を受けており、海外研修の機会もあって行ってきたという。 これを見たBは本人も家庭の事情が豊かではないのに基礎生活受給者ではないため奨学金、海外研修対象者にもならず、むしろ逆差別を受けていると主張した。 1。 本人がCなら、このような支援を受けることについてどう思うか話してみなさい。2.本人がAならばBの主張に対して同意をするのか説明しなさい。3.本人がAで、Bの主張に同意しないならばBをどのように説得するのか話してみなさい。